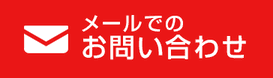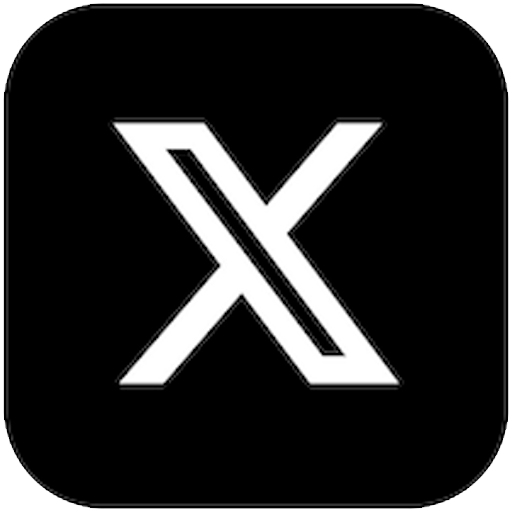札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。
特別法優先の原理です。
これは、同じ種類の法令の間で矛盾を生じさせないために、 認められているルールです。 一般法とは、ある事項について広く一般的に規定した法令をいい、 特別法とは、特定の場合・人・地域などに限定して、 一般法とは異なる定めをした法令をいいます。
そして、特別法優先の原理とは、一般法と特別法が競合する場合は、 特別法が優先的に適用され、特別法と矛盾しない限度において、 一般法が適用されるというルールをいいます。 原則は一般法が適用されますが、特別法がある場合には、 例外として適用されるというイメージです。
例えば民法は私法の一般法であり、その規定は私法関係一般に適用されます。 これに対して、商法は商取引に適用される特別法です。 具体的な例としては、債権の消滅時効期間は一般法の民法では10年です(民法167条1項)。 特別法の商法においては、商事債権の消滅時効期間は5年と定められています(商法522条)。
この場合、特別法優先の原理から、商事債権について民法は適用されず、 商法による5年の消滅時効にかかります。 この原理にはいくつかの注意点が必要になります。
第一に、一般法と特別法の関係は相対的なものであり、 A法はB法との関係では特別法であるが、C法との関係では一般法である場合があります。 雇用関係について言うと、労働基準法は民法との関係では特別法ですが、 地方公務員法との関係では一般法になります。
第二に、ある法令が全体として他の法令の一般法・特別法となる場合だけでなく、 法令中のある規定が他の規定の一般法・特別法となる場合もあるという点です。 会社法295条を見ると、 1項が一般法、2項が取締役会設置会社について定めた特別法という関係です。
特別法は一般法に優先して適用されるため、特別法の存在を見落としていると、 それだけで間違った答えを出してしまう事があります。 そこで、特別法を見つけるための条文上の目印を紹介します。 ただし目印がない場合もありますので注意して下さい。
一般法の目印は下記です。
「他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる」という文言がある場合、 その法律全体が一般法となることを示す目印となります。
特別法の目印は下記です。 「〇〇の特例等を定めるものとする」という文言は、 その法令が特別法であることを示す目印になります。 また、「〇〇の規定にかかわらず」という文言も、特別法の目印です。 上記の目印に注意しながら特別法がないかに気をつけて下さい。 また、目印がなくても常に一般法と特別法の関係に気を配る事が重要です。
当事務所の実績・実例[解決事例]はこちらからどうぞ。
裁判での闘争(攻撃防御)をザックリとしたイメージという観点からは,
「『悪魔の証明』とは?|裁判の勝敗と意外な裁判所のルール」
裁判での主張・立証という観点からは,
「民事裁判の仕組み『権利のための闘争』に勝つ方法」
「証拠」という観点からは,
「なに,証拠がないって?! なければ,作ればいいじゃないか!!」
実際の裁判官の判断プロセスに関心がある方は,
「裁判官の先入感、偏見、独断との闘い」
裁判に負けるタイプという視点からは,
「裁判に〝負ける〟方法」
をご一読ください。